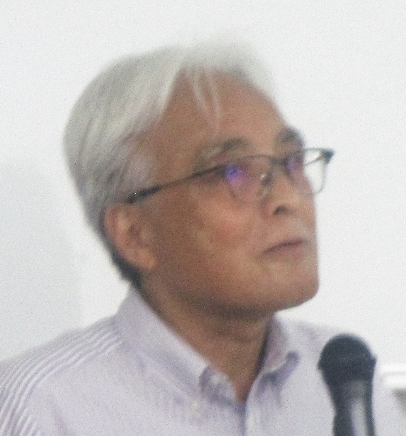2025年9月13日(土)
前田雅人 先生(鹿児島大学教育学部教授、内科医)
テーマ「健康と運動」
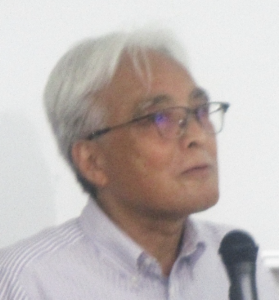
座学に終わるのでなく、すぐにでも行動できる話をしたい。①健康とは、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態、単に病気や虚弱でないことではない。②健康と疾病は、その境界が明確な対比的概念ではなく、身体的、精神的、社会的状態をダイナミックに表す連続的概念の中にある。③健康の水準の低下が徐々にやってくることに気づかないことが多い。一方、本人が病気だと思っているときには、身体的に異常がないと診断されても、健康の水準が高いとはいえない。④社会的に良好な状態とは、社会的役割が果たせること。心身の状態だけではなく、社会人としていくつかの役割を果たしていける状態を「健康」とみなす。「健康」とは全人間的な生活の概念でとらえていく必要がある。⑤人生の目標は「幸せ」。「幸せ」になるためには健康であることが望ましい(健康は手段であり、目的ではない)、夢を持ち続けることが大事、日々目指すべきところを追い求めてほしい。
運動には、行動体力及び防衛体力の向上だけでなく、ストレスの軽減、生活習慣病のリスク軽減などの効果を期待できる。ただし、運動も科学的に理解すべき。「加齢と筋量変化」のグラフ提示。加齢によって最も落ちる角度が大きいのは大腿四頭筋、「老化は足から」。腹直筋も落ちてゆく。運動能力的には、筋持久力と平衡性の低下が著しい(よくつまづく)。メタボリックシンドロームとロコモティブシンドローム、腹囲が大きいと内臓脂肪が多い、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞を起こしやすい。骨・筋肉・関節・靭帯・腱・神経などから構成される運動器の障害のために移動機能が低下、サルコペニア(筋肉量減少)も原因。自分で歩ける、動ける人は寿命が長い。継続的にトレーニングで筋肉を鍛えることが大事。トレーニングの原理、①過負荷、②可逆性、③特異性。種類に有酸素運動(動的、持久的)と無酸素運動(静的、筋抵抗性)。筋肉の動きは骨を刺激、運動は骨も鍛える。筋ポンプ作用、心動態と血圧変化、筋運動と血圧変化、運動の最高反復回数と運動効果の説明。心拍数から求められる運動強度(心拍予備能)は最大酸素摂取量と同等、運動強度と換気量の変化をグラフで説明。運動強度としてMETsの使用、運動と生活活動を併せた身体活動として評価。
65歳以上は3メッツ以上を週15メッツ以上行うことを推奨。
最後に健康づくりのための運動、有酸素運動をメインに筋トレをサブが基本。インターバル速歩、補助運動としてのスローな筋抵抗性運動の具体を紹介、腰痛にも言及。