8月2日、3日の2日間、「造士館講座夏期集中講座」として4本の講座を実施しました。講師の先生方、参加いただいた皆様に敬意を表しつつ、講座の内容をご報告いたします。
2025年8月2日(土)
島津公保(しまづきみやす) 先生
(南九州クリーンエネルギー株式会社代表取締役社長)
テーマ「歴史は地域の資源~歴史を学び歴史を生かす~」

歴史を学ぶとは過去を見つめること、今は過去の結果であり、今が未来を創る。未来は過去の延長線上にある。因果の法則の再認識。歴史は当時そこにいた人の思い・考えによって創られる。
歴史を生かすために取り組んできたことを六つの視点から紹介。①「過去の人たちの精神や志を学び、我々が実践する」、島津日新公いろは歌、島津斉彬の思無邪の心。②「過去の技術の再現」、薩摩切子、磯お庭焼の復元。③「過去の姿を復元し現代の街づくりとして活用する」、鶴丸城ご楼門復元と麓文化の日本遺産、旧芹ケ野金山鉱業事業所をスターバックスへ。④「歴史上の人物の物語をドラマ化」、大河ドラマ誘致。⑤「先人の活動を継承し発展させる」、県立美術館設立へ。⑥「過去を学んで評価し、価値をつける」、集成館事業の世界文化遺産登録。これらの活動を通して、人材の育成、人の交流の活発化を図り、地域の文化力を向上させ、地域の活性化につなげる。具体的な実践事例を示しながら詳細に説明。①「いろは歌」を会社の行動規範に、②「伝統は創造性がなくなったときに途切れる」を信条に薩摩切子の復元・創造、③民間主導で官民連携のご楼門復元プロジェクト、④大河ドラマ誘致の逸話等。⑤江戸期以来のきら星の芸術の系譜紹介。松方幸次郎(松方正義の三男)は「文化の成熟が経済の発展につながる」として美術館を構想。「VUCAの時代」(混沌として先の見えない時代)では論理的・理性的情報スキルは限界、論理から直感へ、理性から感性へ。今こそアート志向。県立美術館の設立、美術館を核とした地域づくりが望まれる。
⑥斉彬の近代化政策(集成館事業)が「明治日本の産業革命遺産」登録へ。自力による試行錯誤の技術導入、海外からの積極的技術導入。短期間で近代化。基盤に日本の高い教育レベルと志を持つリーダーの存在。「日本の近代化は、日本の西洋化ではなく、西洋を日本化したものである」(ピーター・ドラッカー)。登録は鹿児島が主導した国家プロジェクト。活動に関わった者として「思いが出発点、人のネットワーク」を掲げ、稲盛フィロソフィーの「三つの力」を紹介。最後に、「いろは歌」の「いにしえの道をききても唱えても我が行いにせずば甲斐なし」「道にただ身をば捨てんと思いとれ必ず天の助けあるべし」と結ばれた。
2025年8月2日(土)
東川隆太郎(ひがしかわりゅうたろう)先生
(かごしま探検の会代表理事)
テーマ「鹿児島の文化財と向き合う活動を通じて」
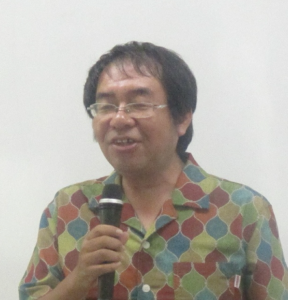
鹿児島には、見残したもの、知らない、活かしていない、埋没しているものがたくさんある。「もったいない」、保存だけでなく活用が求められる。見残した文化財、地域の宝を共有したい、次の世代に残したい、活用してほしい、それらを地域の観光、まちづくり、教育等につなげていこうと2001年度に「かごしま探検の会」を立ち上げた。多様な文化財、何を伝えて、何を残していくのか、所有・保存・継承の主役は住民、自然災害への対応も。地域には眠っている魅力がたくさんある。それを掘り起こして色々な人につなげていくことも活用の一つ。古いだけではなく、一人一人の記憶に残っている物語に気づき、「価値」に気づく過程に地域の人々が関わることが大切。町づくり、地域づくりの真ん中に文化財の物語を。その場面を作るのが私の役割、アカデミックなものを解釈し翻訳し分かりやすく、幅広い色々な人に伝えること。地域の寄り添った保存は、活用や継承を導く。疲れない町づくり、疲れない活動が大切。今の時代のスタイルに寄り添い、寄り添い方を地域で考える。
伊作峠付近に大正5年から昭和41年まで中山小の分校、平治分校。分校跡に創立記念碑。今後、社会現象として別の価値で見える可能性も。吉野のワークショップで吉野台地の井戸から昔の集落、地域の生活の様子が。伊敷地域のワークショップでは、全く知られていない摩崖仏が。喜入には、貝灰(漆喰の原料)をつくる窯。『十島村誌』の「楠木」集落は城跡に位置、奄美・琉球では「城」を「ぐすく」と呼ぶ。中之島の小字と城砦(大城と小城)の図絵から当時の生活が。地形・地質が生活に与える影響、その意味で「ブラタモリ」は秀逸。ストーリーを共有して体感すると腑に落ちる。活火山の米丸マール、約8100年前に噴火。マグマ水蒸気爆発、火災サージと火災物降下、海退で急速に陸化、盆地地形に。泥が深く牛馬の入れない牟田。各地の記念碑は、地域が共同で耕地整理を行った証、地域を知る糸口。米丸地域の耕地整理等を矢継ぎ早に紹介。地域の特徴を表すもので、そこからつながる物語を大事にしている。戦争遺産の紹介、地域で活動している郷土史家の史料の一つ「戦車壕の位置図」。製炭・製鉄が行われていた「火の河原」集落には産業革命遺産につながる別の物語が。校長が地域の拠り所として作った三柱神社、地蔵信仰や麓集落等々、話は尽きることなく続く。鹿児島には見残したもの、すごいものがたくさんある。
2025年8月3日(日)
下豊留佳奈(しもとよどめかな)先生
(オフィスいろは代表、郷土史家)
テーマ「大警視 川路利良の魅力」

川路は、西郷や大久保と時代を同じくする。今まで語られなかった若い時代(禁門の変以前)の活躍を知ってほしい。警察制度の創始者川路が、西郷や大久保の陰に隠れ、鹿児島から、なぜ嫌われたのか。禁門の変で西郷に認められ抜擢されたのがスタート。明治4年の廃藩置県実施に当たって、川路を御親兵に、その後、邏卒総長へ。恩があるにも関わらず西南戦争で西郷を追い詰めた。裏切り者のレッテル、親戚縁者等に累が及んだ。いつ頃から見直しがされてきたのか、最初に銅像が建ったのは霧島市横川町、研究者の私財。その後、鹿児島県警前に彫刻家中村信也作。同じものが中村晋也美術館に。県警前の銅像は、小野次郎県警本部長の意向。台座に「聲無キニ聞き、形無きニ見ル」(『警察手眼』)。生誕地の皆与志町には記念碑、バス停の名前は「大警視」。皆与志小学校の校章は川路家の家紋をモチーフ。校歌に川路利良の名前が。地元で愛されている偉人ではある。
川路より西郷が7歳年長、江戸に出た年齢は川路が先(13歳)、江戸と鹿児島を往来、江戸に詳しい。1851年、斉彬が藩主として初めて薩摩に赴く際、13か所へ飛脚の役割、
健脚。1854年、調練で斉彬に初御目見、貝太鼓役(軍を動かす合図役)。1857年に西洋太鼓を学ぶ、直真影流皆伝も。斉彬が下る際に、腰物箱運搬責任者。1861年、大名・旗本衆の剣術相手役。1862年、生麦事件の際、久光に道具係として随行。1863年、薩英戦争、久光の上京・下向のお供。1864年、禁門の変、町田久成と京に上り、吉井友実についた。久光や息子の珍彦(うずひこ)に認められた。警察官に必要な素養を若い頃から備えていたのでは。
廃藩置県後、東京に3000人の治安部隊、川路は鹿児島で1000人募集。ヨーロッパ研修。
西郷が下野した際は西郷を思う漢詩を。明治7年に警視庁誕生。日本の警察を世界一にとの熱い思いで警察制度。西南戦争、田原坂での官軍抜刀隊の活躍も川路が嫌われた要素。翌年、紀尾井坂で大久保暗殺、翌年、欧米視察、病を得て帰国後まもなく死去。薩摩武士と警察の類似点、先輩・後輩での行動、「外城制度」と交番。歴代警視総監(大警視)はほとんどが鹿児島出身。『西郷南洲遺訓』には「第12条西洋の刑罰に学ぶべきこと」が。「間切横目大躰」には「咎に陥らぬよう仕向け候が第一の事に候」。川路が、その思いを引き継いでいることが、警察としての心得を説いた『警察手眼』からも分かる。
2025年8月3日(日)
池水聖子(イケミズセイコ)先生
(鹿児島県青年会館艸舎理事)
テーマ「子どものよあけと鹿児島~八島太郎と椋鳩十」
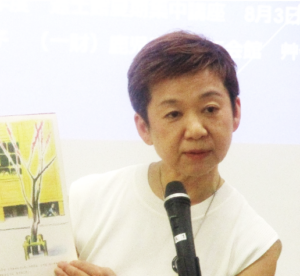
冒頭、八島太郎の代表作「からすたろう」の絵本の朗読、この本が生まれた背景とこの時代のことを話したい。「艸舎(sosya)」は地域再発見のための読書活動を2001年から展開、今年は椋鳩十の生誕120年、2005年の生誕100年には八島太郎を取り上げた。2007年には、八島太郎の出身地の根占と鹿児島市で講演。2008年には、二人を一緒に「金色のふるさと」として、二人は自分の故郷をともに「金色」と。9月、根占の神山小学校に文学散歩。椋鳩十の故郷は信州喬木村、ここに記念館と図書館。2011年、椋鳩十の「母と子の20分間読書運動」50周年を記念して「地域再発見のための読書活動」実施。これまで青年向けの読書活動のなかで取り上げてきた八島太郎と椋鳩十、その取組の数々を紹介。
世界的絵本作家「八島太郎」と、最近ようやく言われるようになった。昨年、「八島太郎」没後30周年記念事業、「子どもたちに伝えたい八島太郎・絵本の中のふるさと」のテーマで講演した。1939年、夫妻で渡米。代表作に根占3部作、1953年『村の樹』、1954年『道草いっぱい』、1955年『からすたろう』(コルデコット賞次席)。「児童絵本とは何か」の中で「児童にとってはいくら立派な絵本であっても立派すぎることはない。児童には最高の絵本を持つ権利があるのである。(中略)戦争の危機に面して深まらざるをえない人命尊重の心情からすれば、これからこそ歴史は、児童絵本の深化にむかっているといえるのではあるまいか」(月刊『絵本』1979)と。1954年、ニューヨーク公共図書館「子どもの絵本週間」で八島太郎の講演を聞いた石井桃子は「私は、日本にも絵本作家ができたと思った」と。瀬田貞二は、「ある雑誌に、八島さんは、自分の経験した幼い日の楽しみを、自分の子にもまた味わわせたかった。究極のところ、この世は美しく、生きることはすばらしい。人を信じようという気持ちを、私は絵本に託すのだと、八島さんは書いています」(『絵本論―瀬田貞二 子どもの本の評論集―』1985)。石井も瀬田も、日本の子どもの本の草創期を開拓した人たち。
「彼の精神は、ごうごうと、音立てて燃えていた。(中略)タローの作品は、この烈しい火を感じなくては理解出来ないであろう」(「タローの人と作品」椋鳩十)。最後に石井桃子の自筆色紙の言葉を紹介、「子どもたちよ、子ども時代をしっかりとたのしんでください。おとなになってから、老人になってからあなたを支えてくれるのは子ども時代の『あなた』です」。



